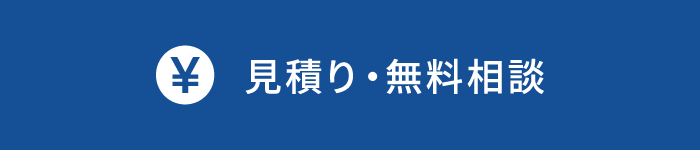点検時間を年間約4,000時間削減。連続監視で故障予知も可能に。【導入事例|ダイキン工業株式会社】
- IoT 角度センサ
- データロガー

1933年に日本で初めて「フッ素化学」に取り組んだダイキン工業株式会社。フッ素化学業界のパイオニアとして、家庭用品から自動車、半導体まで幅広い分野で欠かせない素材を世界へ提供し、豊かな社会を支えてきました。
一方、産業界では人手不足や人材の高齢化といった課題があり、その解決が急務となっています。同社では、その対応策の一つとしてSIRCのIoT角度センサユニットを導入。設備の大規模な改造を行わず、年間約4,000時間の業務効率化とデータ活用による安定操業を実現しました。
今回は、その具体的な取り組みに加え、SIRCとダイキン化学事業部(以下、ダイキン化学)が協業によって進めた防爆モデルの開発プロセスについてもお話を伺いました。
お話を伺った方
ダイキン工業株式会社 化学事業部
課長 岡本様(写真中央)
村田様(写真右)
青谷様(写真左)

導入商品
課題背景
・巡回目視点検に多くの工数がかかり、現場の大きな負担となっていた
・さまざまな理由から連続監視の必要性が高まったが、設置工事や費用の制約がありシステム導入のハードルが高かった
・従来の巡回目視点検は8時間ごとの確認にとどまり、設備異常の早期発見が難しかった
成果
1.年間約4,000時間の業務効率化を実現
2.連続監視により設備異常を早期に発見できるようになり、修繕費の削減につながった
3.効率化により創出した時間を、若手教育や改善活動に充てられるようになった

導入前の課題
「点検業務にかかる負担を減らし、業務の効率化を進めたい」
―化学プラントにおける、点検業務について教えてください。
化学プラントの点検業務には、機器からの漏洩や異音の感知といった「五感」や「経験」を要するものに加えて、圧力や温度など現場計器の数値確認があります。「巡回目視点検」といって、担当者が画板を手に巡回し、現場計器の数値を目視で読み取って手書きで記録しながら、振動や臭い、温度の変化などを確認して異常の有無を判断してきました。

―従来の点検方法には、どのような課題があったのでしょうか?
数値の読み間違いや転記ミスといったヒューマンエラーが起きやすく、担当者によって判断にばらつきが生じることも。巡回目視点検は工数がかかるうえ、単純作業の繰り返しによって形骸化しやすいという課題もあります。
―点検業務は、全体の業務の中でどのくらいの割合を占めているのでしょうか?
バッチプラント※で約20%、連続プラント※で全体の約30%を占めています。
手書き転記や帳票入力、傾向管理、日報作成といった事務作業も含まれるため、現場にとっては大きな負担となります。少子高齢化を背景とした人材不足が進むなか、定年延長などで対応は進められています。一方、真夏や真冬の巡回、さらには夜勤を伴う点検は体力的な負担が大きく、現場全体の課題となっています。
特に連続プラントでは、原料の投入や抜き出しといった手作業がほとんどないため、計器の値を見ながら予兆や変化を見極めることが主な業務になります。つまり、業務の大半を占める点検業務を効率化できれば、現場の負担を大きく減らせます。
※バッチプラント
すべての原料を装置に仕込み、特定の量の材料を一度に処理するプラント。小規模生産や多品種少量生産の時に採用される。
※連続プラント
原料を連続的に装置へ供給し、装置出口から生成物を連続的に取り出すプラント。定常状態を保ち、大量処理に適しており、工業的に広く採用されている。
―従来の点検データには、どのような課題がありましたか?
従来の巡回目視点検時に記録されるのは「点」のデータでした。設備の状態変化を連続的に把握することができないため、異常の予兆をつかみにくく、対応も後手に回りやすいという課題がありました。
導入の経緯と過程
「操業を止めることなく取り付けられる点が魅力」

―御社におけるDX推進についてお聞かせください。
DXを通じて人手不足への対応や点検業務の効率化を進め、安全・安定操業を目指しています。
2023年にプラント内にIoT専用のWi-Fi環境を整備し、各種センサを設置して点検業務の効率化を進めています。加えて、センシングしたデータを蓄積・解析することで、設備の異常変化をいち早く見つけるなど、データを活かした取り組みも行っています。
少子高齢化による今後の労働力不足は明らかですから、さまざまな選択肢を持ちながら業務負荷を削減していくことが重要だと考えています。

―IoT角度センサ導入以前に抱えておられた課題をお聞かせください。
建設当初はアナログメーターを使用していましたが、プラントの老朽化に伴う安全性の向上施策や効率改善、顧客からの品質要求の変化により、連続監視が必要となる場面が増えてきました。そのたびにDCS※に取り込むための設備改造を行ってきましたが、大規模な投資が避けられずハードルとなっていました。
24時間操業するプラントでは、工事のタイミングも限られます。年に一度の定期整備時にしか設置作業が行えず、迅速な対応が難しいという制約もありました。
※DCS(分散制御システム)
プラント・工場の製造プロセスや生産設備などを監視・制御するための専用システム。
―防爆エリア※における課題もあったのでしょうか?
後付けできる防爆対応機器の選択肢が限られており、既存設備への導入はほとんど断念されていました。最大の理由はコストです。防爆仕様になると価格が10倍ほどに跳ね上がり、その投資に見合うかどうかの判断が難しく、なかなか採用に至りませんでした。
※防爆エリア
化学プラントなどで可燃性物質が存在し、火災や爆発の危険がある区域のこと。
―角度センサを初めて見た時の印象は?
「ペットボトルのキャップみたい」という印象を持ちました。コンパクトで、設備を解体せずに設置できる点が魅力に感じました。

―設置にあたって、どのような手順を踏まれたのでしょうか?
アナログメーターの位置特定から始め、ゲートウェイの設置場所の選定、ネットワークや機器構成の検討、データ受信側の設定、センサの設置・調整までを段階的に進めました。
―その過程で、特に苦労された点はありますか?
操業データはセキュリティ上の理由で社外クラウドに保存できないため、通信環境の整備が課題となりました。なかでもPCサーバー周りの対応に苦労したことを今でもよく覚えています。IoTセンサの本格導入は当社にとって前例のない取り組みでしたので、これまでにない経験になりました。
他にはBluetoothの受信状況が確認できないことや、センサの設定確認・変更がローカルでしか行えないことなど、いくつかの課題がありました。その都度SIRCに改善要望を伝えたことで製品に反映され、角度センサは進化し、現在ではほとんどの課題が解消されています。
この取り組みは茨城県にある鹿島製作所にも展開したのですが、スムーズに導入することができました。

防爆モデル開発の歩み
「化学業界で広く利用される製品を目指して」
―その後、ダイキンとSIRCは資本業務提携を結び、防爆モデルの開発に着手しました。
当時、市場には防爆対応の後付け可能な角度センサが存在しませんでした。SIRCが製品化を進めるには国の防爆認定が必要で、実証実験に適したフィールドが無いということでした。
一方で、ダイキン化学としては防爆製品をいち早く導入したいという思いがあり、両社のニーズが合致したことで資本業務提携を結び、SIRCのセンサをダイキン化学のプラントで評価する取り組みが始まりました。
―開発の過程では、具体的にどのような課題がありましたか?
防爆エリアは非防爆エリアに比べて設備が密集し、建屋や金属の壁で仕切られているため、電波が遮断されゲートウェイまで届かないという課題がありました。
―そうした課題には、どのように向き合われたのでしょうか?
センサの電波強度の改善やゲートウェイのソフト改良を進めてもらいました。化学業界で広く利用される製品にするには、センサだけでなく防爆仕様のゲートウェイもラインナップすべきだと進言しました。
ミーティングでは率直に意見を伝える機会が多くありましたが、「ダイキン化学だけが特殊なのではなく、化学プラントの現場はこういう環境なのだ」と、業界標準として通用する製品にするために、一貫して伝え続けました。
そうしたやりとりの積み重ねによって試作品は改良を重ね、形を変えながら進化し、2024年3月にSIRCからの発売に至りました。
IoT角度センサユニット 防爆対応モデル発売開始のプレスリリースは こちら
導入後の成果
「点検時間を年間約4,000時間削減。連続監視で故障予知も可能に」

―IoT角度センサ導入によって、改善されたことを教えてください。
非防爆プラントの一例では、2020年度に約7,000時間かかっていた点検業務が、2025年度には2,500~3,000時間にまで減る見込みです。アナログメーターの目視確認や点検表への記録、Excelの管理帳票へ転記作業が大幅に削減された結果です。手書きによる読み間違いや入力ミスもなくなりました。
―削減された時間はどのように活用されていますか?
改善活動やグローバル拠点の支援など様々ですが、特に教育の面が大きいですね。
ベテランのメンバーが体力的な理由から三交代勤務を離れるケースが増え、現場の若年化が進んでいます。その結果、経験や力量の低下が否めず、若手教育が急務となっています。効率化によって確保できた時間を、教育や人材育成に充てられるようになりました。
―そのほかに、どのような効果を実感されていますか?
はじめは「点検工数の削減」に目が向いていましたが、次第にデータ活用の価値が見えてきました。
例えば、廃液からガスを回収する装置では、圧縮機の弁や配管の詰まりが繰り返し発生し、修繕費がかさんでいました。そこで、3カ所の圧力計を同時に連続監視し、圧力上昇を「詰まりの予兆」として捉えることで故障を未然に防止し、結果として修繕費の削減につながりました。

また、冷凍機はプラントにとって重要なユーティリティですが、従来の巡回目視点検では8時間ごとの確認しかできず、異常の発見が遅れることがありました。特に夏場の想定外の暑さは大きなリスクで、冷凍機の異常は製品の品質やプラントの安定操業に悪影響を及ぼします。現在はリアルタイムで変化を捉えられるため、気候変動による想定外の暑さにも早期に対応できています。
―現場ではデータをどのように見える化しているのですか?
職場のモニターに設置場所の図を表示し、誰でも確認できる仕組みを整えています。リアルタイムで可視化できるようになったことでオペレーターの気づきにつながり、新しいアイデアが生まれるなど、付加価値の創出にもつながっています。

改善活動の経験がなかった入社3年目の若手社員に、センサの導入を任せたことがありました。準備や各所との調整を通じて多くの人と関わりながら改善に取り組んだことが、貴重な成功体験となったようです。
その後、自分が担当するプラントの不具合にも積極的に目を向けるようになり、次々とアイデアを出したり、自らデータを収集したりするようになっていきました。改善活動を通じて自信を深め、主体性を持って成長していく姿が見られた出来事でした。

さらなる改善に向けて
「安全で、価値創造に集中できる環境をつくりたい」

―今後のDX推進についての展望をお聞かせください。
DXはあくまで目的ではなく手段です。さまざまなセンサや仕組みを活用していくことで単純作業を減らし、人が価値を生むための工夫や意思決定に時間を割ける環境をつくりたいですね。
また、「ここで働きたい」と思ってもらえる職場づくりも大事なテーマです。特に夜勤業務は負担が大きく、暗闇での巡回や悪天候の中高層階を昇り降りする作業には危険が伴います。こうした現場の厳しさを取り除き、より安心して働ける環境を実現していきたいです。
―同様の課題を抱える企業様へメッセージをお願いします。
IoT角度センサを活用することで、設備を大きく改造することなく、効率化やデータ活用による安定操業の仕組みを実現できました。私たちの取り組みが、課題解決に取り組む企業様にとって少しでも参考になればうれしく思います。
同じ課題を抱える企業の皆様とは、情報交換や現場見学を通じてお互いに学び合える場を持ちたいですね。SIRC製品ユーザー同士の交流も、新しい気づきや改善のヒントにつながるはずです。
こうした取り組みを積み重ねることで新しい価値を生み出し、化学産業全体の発展に貢献していきたいと考えています。

ダイキン工業株式会社
創業 1924年10月25日
代表者 代表取締役社長 兼 COO 竹中 直文
本社所在地 大阪市北区梅田1-13-1
大阪梅田ツインタワーズ・サウス
事業内容 空調・冷凍機、化学、油機、特機、電子システム
HP https://www.daikin.co.jp/
\ こちらの事例もおすすめ /
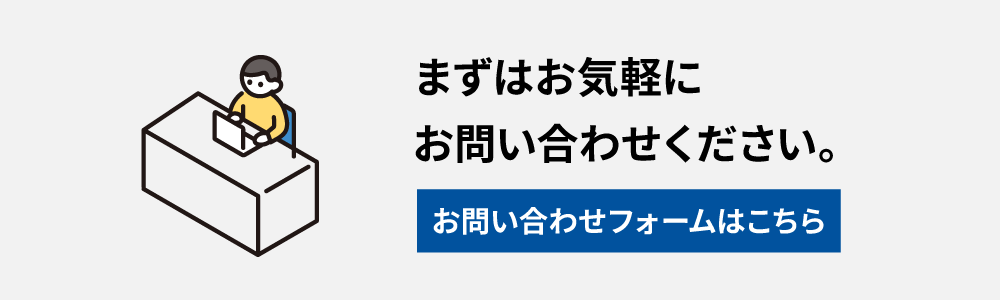
お電話でのお問い合わせ ☎ 06-6484-5381 受付時間 9:00~17:30(土日・祝日除く)